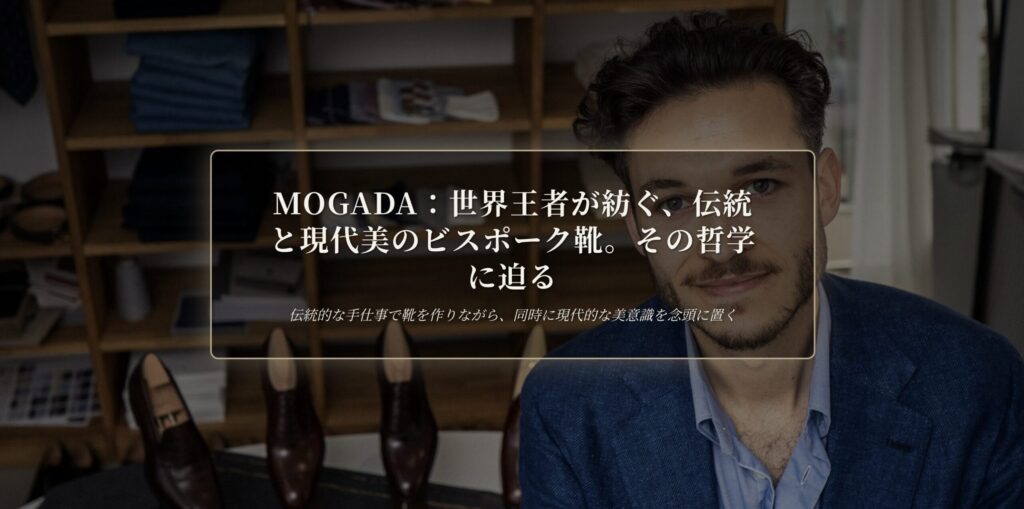フィレンツェの木象嵌職人・望月貴文が紡ぐ、伝統と革新の物語
2025-11-01 公開/2025-11-01 更新/著者: 金子真之
掲載写真は提供または許諾のうえで使用し、本文は関係者の確認を経ています。
フィレンツェのオルトラルノ地区、サン・フレディアーノの石畳を歩くと、Via dei Cardatori 20rに小さな工房が佇んでいる。ここは望月貴文が営む「ZOUGANISTA(ゾウガニスタ)」──フィレンツェで数少ない木象嵌専門工房である。かつて街のあちこちにいた木象嵌職人は今や彼ただ一人となり、2014年の開業時には専門で象嵌を生業とする職人はフィレンツェに存在しなかった。本記事では、作りの正確性(Craft)、使い心地(Comfort)、手入れの容易性(Care)、価格と維持費(Cost)、継続供給と修理性(Continuity)という5Cの観点から、望月の仕事と工房の実態を整理する。屋号「Zouganista」は、Zougan(象嵌)+ -ista(伊:専門職)を組み合わせた造語で、“Born in Tokyo. Made in Florence.”という彼の合言葉そのままに、日本で生まれフィレンツェで磨いた技術で新しいモノを生み出していく姿勢を示している。
動画:砂焼きで陰影をつける象嵌(Zouganista公式YouTube)
フィレンツェで消えゆく伝統を一人で守る決断

2013年、望月が自営業タイプの滞在許可証を取得し開業届を提出した時点で、フィレンツェには木象嵌を専門とする職人が一人もいなかった。ベテランの家具修復職人の中に技術を持つ者が3〜4人程度いるのみで、象嵌そのものを生業とする者は皆無だった。この状況は世界中の古都で共通しており、技術の衰退は避けられない流れに見えた。しかし望月は、師匠のレナート・オリヴァストリから学んだ技術と、家具メーカーでの営業経験から得た市場感覚を組み合わせ、独立を決断した。彼の仮説は明快だった──伝統技法を現代的なアイテムに応用すれば、需要を喚起できる。検証は工房開設後すぐに始まった。初の土曜日、散歩中の女性が外から工房を覗き込み、ストックしていたシガーレットケースにロゴの象嵌を依頼した。この初オーダーが、仮説の正しさを裏付ける最初の証拠となった。結論として、継続供給という観点では、彼が数少ない専門職人であることが逆に強みとなり、技術の希少性が価値を生み出している。
営業マンから職人へ──運命を変えた糸ノコギリとの出会い

1979年東京生まれの望月は、大学で経営学を学び、インテリアの専門学校を経て家具メーカーで営業職に就いた。手先が特別器用だったわけでも、美術的な訓練を受けていたわけでもない。しかし2007年、27歳でフィレンツェに渡り、翌2008年にオリヴァストリ氏のもとでアンティーク家具の修復を学び始めた際、運命的な瞬間が訪れた。象嵌用の糸ノコギリを初めて手にした瞬間、「心とからだにピタッとハマった」と彼は振り返る。最初からある程度上手くできてしまったという事実は、彼自身も不思議に感じている。この体験は、作りの正確性を支える基礎となった。糸ノコギリでの切り出しは、0.7〜0.8mm厚の突板を5枚重ね、ミリ単位のパーツを生み出す作業で、1つの作品に1週間を要することもある。大変な集中力と根気が求められるが、望月にとってこの道具は自己表現の手段そのものとなった。営業経験は工房運営の判断基準を与え、職人技術は作品の質を保証する。この二つの要素の組み合わせが、彼の独自性を形成している。
0.7mmの突板に宿る、電気のない時代の技術

望月が用いる象嵌技法は、「電気のない時代と変わらない」本質を保っている。使用する突板は0.7〜0.8mm程度の厚さで、これを5枚重ねて糸ノコギリで切り出す。素材はローズウッド、カーリーメープル、バーチ、ウォルナット、マホガニー、エボニー、ウェンゲ、パープルハート、オーク、ポンメレなど多岐にわたる。接着には膠(にかわ、イタリア語でcolla di bue)を用い、仕上げにはシェラックやフレンチポリッシュといった伝統技法を採用する。これらの工程は18世紀の職人が行っていた方法と本質的に同じであり、電動工具や化学接着剤に頼らない純粋な手仕事である。作りの観点では、この伝統技法が作品の耐久性と修理性を保証する。膠は水分で再活性化できるため、将来的な修復が容易であり、シェラック仕上げも研磨と再塗布で元の輝きを取り戻せる。一方で、この手法には失敗のリスクも伴う。突板は薄く脆いため、切り出し時の力加減を誤ると割れてしまう。また膠の温度管理を誤ると接着力が低下し、作品の耐久性が損なわれる。望月はこれらの失敗を回避するため、素材の状態を常に観察し、湿度や温度に応じて作業手順を微調整している。
木の色に限りがある中で、コントラストを最大化する設計思想

象嵌の最大の難しさは、木を切り出す作業そのものではなく、「木の色に限りがある中で、どうコントラストをつけるか」にあると望月は語る。板目、柾目、コブといった木目の方向性を組み合わせ、光の当たり方で色調が変化する効果を計算に入れながら、視覚的なコントラストを最大化する。この設計思想は、作りの正確性と直結する。例えば、代表作「Panorama Firenze」では12種類の木を用いてフィレンツェの市街を表現しているが、建物の陰影や空の明るさは、木目の方向と素材の選択だけで再現されている。色調の対立軸比較で言えば、明るいカーリーメープルと暗いエボニーの組み合わせは最もコントラストが強く、初心者でも扱いやすい。一方、ウォルナットとマホガニーのような中間色同士の組み合わせは、微妙な木目の違いでしか差を出せないため、高度な技術と経験が必要となる。望月は後者のような難易度の高い組み合わせを好み、繊細な表現を追求する。この選択は、価格帯にも反映される。単純な色対比の作品は比較的短時間で完成するが、微妙な階調を表現する作品は制作時間が倍増し、価格も上昇する。
サンドバーニングと膠──フィレンツェ伝統の仕上げ技法

フィレンツェ伝統の「サンドバーニング(砂焼き)」は、象嵌に陰影を与える独特の技法である。熱した砂に木材を押し当てることで、化学染料を使わずに自然な焦げ色を生み出す。この技法の利点は、木材本来の質感を損なわず、経年変化も自然に進行する点にある。手入れの容易性という観点では、サンドバーニングで着色された部分は研磨しても色が抜けにくく、再仕上げの際にも元の色調を再現しやすい。一方、失敗のリスクも高い。砂の温度が高すぎると木材が炭化して脆くなり、低すぎると十分な色が出ない。望月は砂の温度を手の感覚で判断し、木材の種類ごとに押し当てる時間を調整している。接着に用いる膠も、伝統技法の核心である。膠は動物の皮や骨から抽出されたコラーゲンで、温めると液状になり、冷えると固まる。この可逆性が修理性を保証する。将来的に象嵌が剥がれた場合でも、水分と熱を加えれば膠を再活性化でき、元の位置に接着し直すことができる。現代の化学接着剤では、一度固まると剥がすことが困難で、修理時に作品を傷める危険性が高い。膠の使用は、継続供給と修理性を重視する望月の姿勢を象徴している。
真鍮線と金継ぎ意匠──日本とイタリアの美意識の融合

望月の作品には、真鍮線を用いた装飾が随所に見られる。これは日本の金継ぎ技法に着想を得たもので、割れや欠けを金で修復し、その痕跡を美として昇華させる日本的感性を、木象嵌に応用したものである。真鍮線は木材と異なる素材であり、光の反射で強いアクセントを生み出す。タイ ユア タイ フローレンスの店内にある巨大な箪笥の修復では、望月が真鍮の象嵌でロゴを施工し、木材だけでは表現できない輝きを加えた。この技法は、作りの正確性と使い心地の両面で意味を持つ。真鍮線は木材よりも硬く耐久性が高いため、頻繁に触れる部分に用いることで摩耗を防ぐ。例えば名刺入れやコインケースの縁に真鍮線を配置すれば、長期使用でも形状が保たれる。一方、真鍮は経年変化で酸化し、緑青を生じることがある。これを美しい経年変化と捉えるか、劣化と捉えるかは使い手の価値観による。望月は顧客に対し、真鍮の経年変化の特性を事前に説明し、定期的な磨きで輝きを保つ方法を伝えている。この透明性が、手入れの容易性を高めている。とりわけ、1700年代のイタリアン・ウォールナットを土台に日本の風神雷神を重ねた作品は、時と場所を超える協奏であり、虫喰いの穴に真鍮線を埋めて夜空の星に見立てる発想に、金継ぎの哲学が息づく。「日本で生まれ、フィレンツェで作る自分にしか生み出せない」と彼が語る所以だ。
靴木型から時計ケースまで──曲面への挑戦が拓く新領域

伝統的な木象嵌は平面の家具や装飾パネルに施されることが多いが、望月は曲面への象嵌に積極的に取り組んでいる。代表作「Carnevale」は、靴木型にカーニバル仮面のモチーフを象嵌したもので、立体的な曲面に沿って突板を貼り込む高度な技術が要求される。靴木型や帽子型のオブジェ、ランプシェード、さらには時計ケースやスケートボードといった実用品まで、曲面を活かした作品は望月の独自性を示している。曲面への象嵌は、平面とは異なる技術的課題を伴う。突板は薄く柔軟性があるものの、急激なカーブには追従しにくい。望月は突板を水で湿らせて柔軟性を高め、曲面に沿って少しずつ接着していく。この工程は時間がかかり、失敗すれば突板が破れる。しかし成功すれば、平面では得られない立体的な視覚効果が生まれる。使い心地という観点では、曲面への象嵌は実用品の機能性を損なわないよう設計される。時計ケースであれば、蓋の開閉に支障が出ないよう象嵌の厚みを調整し、スケートボードであれば、足の接地面に象嵌を施さず滑り止め機能を保つ。この実用性と美しさの両立が、望月の作品が世界のウェルドレッサーたちから注目される理由である。
3500ユーロの時計ケースが示す、価格と価値の関係

ブリオ ベイジンのジョージ・ワン氏がオーダーした時計ケースは、3500ユーロ(約55万円)という価格で制作された。この価格は、ペンダントトップ80ユーロ、コインケース300ユーロといった小物と比較すると桁違いに高い。しかし価格と価値の関係を検証すると、この金額は妥当であることがわかる。時計ケースの制作には、0.7〜0.8mmの突板を5枚重ねて切り出す作業だけで1週間を要し、さらに曲面への接着、サンドバーニング、シェラック仕上げといった工程が続く。総制作時間は3〜4週間に及び、望月の時給換算では決して高額ではない。価格帯による対立軸比較では、小物は短時間で完成し、デザインもシンプルなため、初めて象嵌作品を購入する顧客に適している。一方、時計ケースや家具といった大型作品は、複雑なデザインと長時間の制作を要するため、象嵌の価値を深く理解した顧客向けである。維持費という観点では、象嵌作品は定期的な手入れが必要だが、その手順は単純である。乾いた布で埃を拭き取り、年に1〜2回、蜜蝋またはミンクオイルを塗ることで輝きが保たれる。修理が必要な場合も、膠の可逆性により、元の状態に戻すことが可能である。この低い維持費と高い修理性が、長期的なコストパフォーマンスを高めている。

工房そのものが文化遺産──17世紀の素材が蓄積される場

イタリアの家具修復文化において、工房は家業というより工房自体が受け継がれていく存在である。17世紀の家具を修復するためには17世紀の素材が必要であり、歴史のある工房には素材が世代を超えて蓄積されていく。望月の工房も、開業から11年を経て、様々な時代の突板や金具、膠や顔料といった素材が集まり始めている。工房そのものの価値が高まることで、技術の継承がより確実になる。継続供給という観点では、この素材の蓄積が重要な意味を持つ。例えば、20年前に制作した象嵌作品の修理依頼があった場合、当時と同じ種類の突板が工房に残っていれば、完全に元の状態に復元できる。しかし素材が失われていれば、近似した木材で代用するしかなく、修理の質が低下する。望月は工房探しに20〜30件の物件を回り、最終的にVia dei Cardatori 20rを選んだ。この場所はドゥオモやポンテ・ヴェッキオから徒歩10〜15分という好立地でありながら、家賃が比較的手頃で、素材を保管するスペースも十分に確保できた。工房の立地と広さは、長期的な事業継続の基盤となっている。
アジア人への偏見を乗り越えた1年間の沈黙

2008年、オリヴァストリ氏のもとで学び始めた当初、望月はアジア人全体に対する偏見に直面した。挨拶をしても返ってこない状況が1年ほど続き、精神的に厳しい時期だった。職人の世界はコネが重視され、外部から入り込むことは容易ではない。ましてやアジア人が伝統技術を学ぶことに対し、懐疑的な視線が向けられた。しかし望月は、技術の習得に集中し、誠実に仕事をこなすことで、徐々に信頼を得ていった。一方で、滅びゆく技術を日本人が受け継いでくれることに興味を持つ人々もいた。フィレンツェ市公式観光サイトFeelFlorenceや、Michelangelo FoundationのHomo Faber Guideに掲載されたことは、彼の技術が公的に認められた証である。2015年には世界的なインテリア誌AD Italiaの「40歳以下のクリエイター20人」に選出され、国際的な評価を得た。この経験から得られる教訓は、技術の価値は国籍や人種を超えるということである。絶対的に技術者が不足している現実と、技術自体に価値を感じる人々の存在が、望月の継続を支えている。
Airbnb体験プログラム──2時間で象嵌の本質を伝える設計

望月はAirbnb Experienceで「Craft a wooden puzzle」という体験プログラムを提供している。所要時間は約2時間、最大4名までの少人数制で、イタリア語、英語、日本語に対応する。内容は象嵌の歴史説明から始まり、突板の選定、切断、組み上げ、サンドバーニング、仕上げまでを一通り体験できる。レビュー評価は5.0と高く、価格は約13,140円(時期や通貨設定で変動)である。この体験プログラムは、象嵌の本質を短時間で伝えるよう設計されている。参加者は自ら突板を選び、糸ノコギリで切り出し、膠で接着する。この一連の作業を通じて、作りの正確性がいかに重要かを体感する。失敗例としては、切り出し時に力を入れすぎて突板を割ってしまうケースが多い。望月はこの失敗を防ぐため、最初に力加減のデモンストレーションを行い、参加者が実際に切る前に何度も練習させる。回避策としては、突板を水で湿らせて柔軟性を高めることが有効である。体験プログラムは、象嵌の普及という観点でも意義がある。参加者の多くは象嵌を初めて知る人々であり、この体験を通じて技術の価値を理解し、将来的な顧客となる可能性がある。
修理性と継続供給──工房が20〜30件の物件探しを経た理由

2014年の工房開設に向けて、望月は20〜30件の物件を回った。この徹底した物件探しは、修理性と継続供給を重視する彼の姿勢を反映している。工房に求められる条件は複数あった。第一に、素材を保管するスペースが必要である。突板や膠、顔料といった素材は湿度や温度の影響を受けやすく、適切な保管環境がなければ劣化する。第二に、作業音や粉塵が近隣に迷惑をかけない立地が必要である。糸ノコギリの音は比較的静かだが、研磨作業では粉塵が発生する。第三に、顧客がアクセスしやすい場所でなければならない。ドゥオモやポンテ・ヴェッキオから徒歩圏内という立地は、観光客や地元住民が気軽に訪れることができる。最終的に選ばれたVia dei Cardatori 20rは、これらの条件を満たしていた。修理性という観点では、工房の継続性が重要である。顧客が10年後、20年後に作品の修理を依頼する際、工房が存在していなければ修理は困難になる。望月は長期的な視点で工房を運営し、素材の蓄積と技術の継承を進めている。継続供給の失敗例としては、工房が閉鎖され、修理を受け付けられなくなるケースがある。回避策としては、家賃が手頃で安定した収入源を確保し、工房の財務基盤を強化することが不可欠である。
AD Italiaが選んだ「40歳以下のクリエイター20人」の意味

2015年、望月は世界的なインテリア誌AD Italiaの特集「今のインテリアを変える40歳以下のクリエイター20人」に選出された。この選出は、彼の仕事が単なる伝統技術の継承ではなく、現代的な価値を生み出していることを示している。AD Italiaは「Takafumi Mochizuki è nella lista dei 20 creativi under 40 che stanno cambiando volto alle nostre case(望月貴文は、私たちの家の顔を変えている40歳以下の20人のクリエイターのリストに入っている)」と評した。この評価の背景には、伝統技法を現代的なアイテムに応用する彼の姿勢がある。靴木型やスケートボード、時計ケースといった作品は、象嵌を美術館の中だけでなく、日常生活の中に持ち込んだ。Vogue Italiaは「Mochizuki unisce la minuziosità dell’arte giapponese all’estro e alla creatività del design italiano(望月は日本の芸術の緻密さとイタリアンデザインの創造性を結びつけている)」と評し、Vanity Fairは「Takafumi riesce a scolpire forme perfette, che vengono impreziosite da intagli di mogano, betulla, ebano. Fino a creare dei pezzi unici(望月は完璧な形を彫刻し、マホガニー、バーチ、エボニーの象嵌で装飾し、唯一無二の作品を生み出している)」と称賛した。地元でも「Made in Florence」を体現する職人の一人として認められ、技術を世界へ伝えてほしいという声が寄せられている。これらの評価は、作りの正確性と現代的デザインの融合が、国際的に認められたことを意味する。

Summary
望月貴文の仕事は、作りの正確性、使い心地、手入れの容易性、価格と維持費、継続供給と修理性という5Cの観点から見ると、伝統技法の本質を保ちながら現代的な価値を生み出している。0.7mmの突板を糸ノコギリで切り出し、膠で接着し、サンドバーニングで陰影をつけ、シェラックで仕上げる工程は、電気のない時代と変わらない。しかし靴木型や時計ケース、スケートボードといった現代的なアイテムへの応用は、象嵌を日常生活の中に持ち込んだ。真鍮線を用いた金継ぎ的意匠は、日本とイタリアの美意識を融合させた独自の表現である。工房そのものが文化遺産として素材を蓄積し、長期的な修理性を保証する。Airbnb体験プログラムは、象嵌の本質を2時間で伝え、次世代への普及を図る。AD Italiaの選出は、彼の仕事が国際的に認められた証である。次に読むべき観点は、望月がどのように技術を次世代に継承していくかである。現時点で彼は数少ない専門職人であり、技術の継承は喫緊の課題となっている。
工房情報
ZOUGANISTA di Takafumi Mochizuki
住所: Via dei Cardatori 20r, 50124 Firenze, Italy
電話: +39 331 822 3767
メール: mail@zouganista.com
ウェブサイト: www.zouganista.com
営業時間: 10:00–19:00(要事前連絡推奨)
SNS・オンライン
YouTube: ZOUGANISTA / イタリア職人修行
Instagram: @zouganista
X (Twitter): @lunapienabytaka
Facebook: Zouganista
note: フィレンツェでの職人生活に至るまでの回想録
Blog: Ameba Blog
ご購入・オーダー
Instagramや各SNSのメッセージ、またはメールで随時受付。
年に一度の日本帰国時に開催する展示会でもご購入・オーダー可能。
体験プログラム
Airbnb Experience「Craft a wooden puzzle」
所要時間: 約2時間 / 最大4名 / 対応言語: イタリア語・英語・日本語
価格: 約¥13,140/人(時期により変動)
スポンサー募集のご案内
「The Makers Guild」は、クラフトや靴文化を共有する国際的なコミュニティサイトです。ブログは日本語を含む7か国語で配信し、世界中の読者に靴文化の魅力をお届けしています。現在、私たちの理念に賛同し活動を応援してくださるスポンサー様を募集しています。詳細やご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。